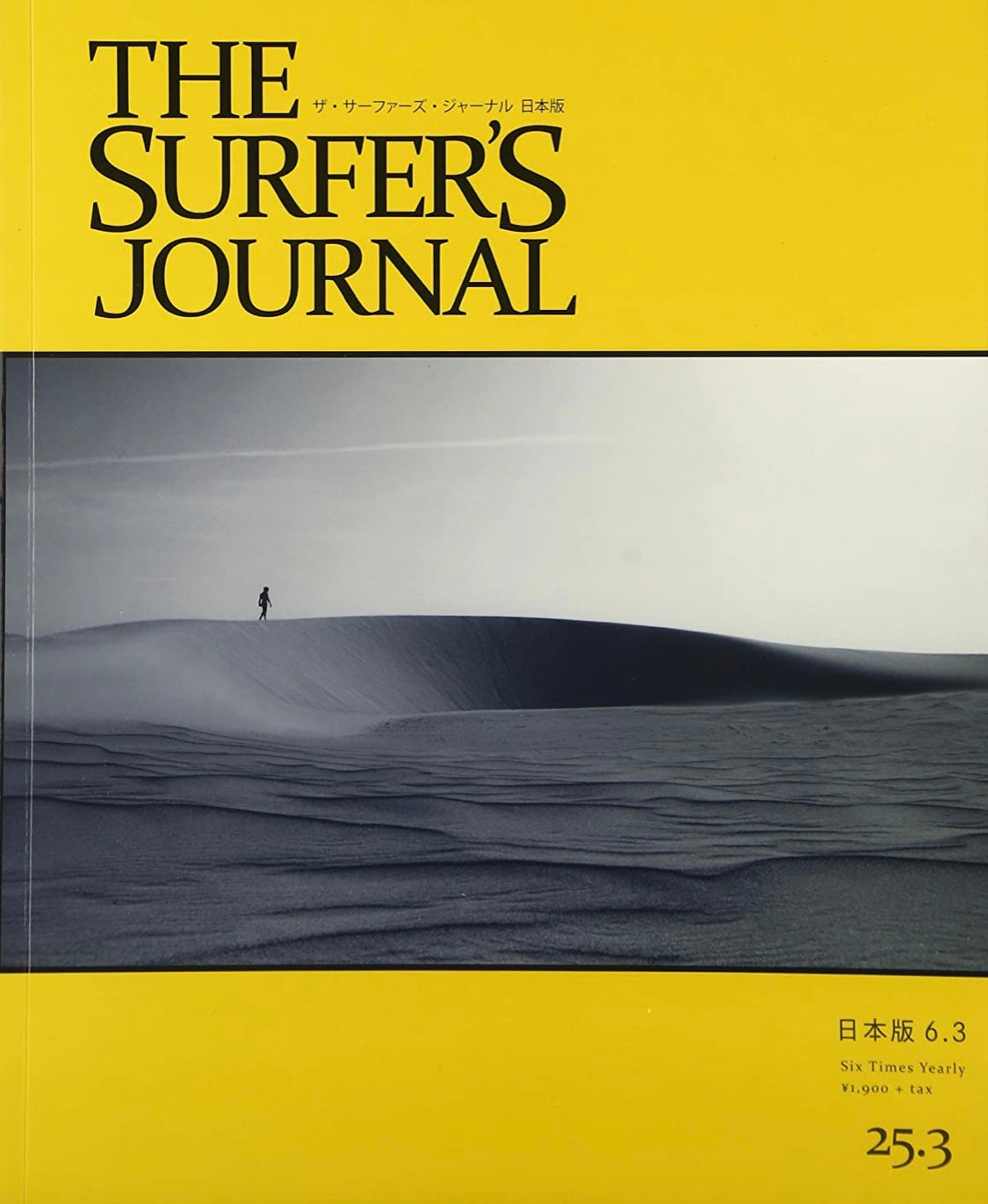
6.3 / ザ・サーファーズ・ジャーナル日本版
税込み価格
Town Abides
「タウンは変わらず」
ワイキキのリーフ、ストリート、人々、周辺地域。心と身体の帰還
文:デビッド・ウォング
ぼくは島から7年間も離れ、メインランドに住みついたケイキ・オ・カ・アイナだった。ぼくはようやくここへ帰り、砂をかぶりひび割れたカイザースの駐車場を歩いていた。シャワーの前を通り、小さなビーチへ向かう。ポイドッグをなでて、深呼吸してストレッチをした。サムライ全員が撃たれる映画の話をしているアンクルがいた。あっという間に干からびる水たまりに捕まった蜂がもがいている。チャンネルをカヌーが走っていった。岩の上では大きなカーキ色のパンツを穿いた中国人が太極拳をおこなっている。ロングボードのワヒネがあまりにも美しく波に乗るので、ぼくは若返った気分でちょっとウキウキした。死んだリーフは沈んだ墓地のようだった。
Spacetime
「スペースタイム」
波の一生を一枚の写真で表現する写真家、ジェイ・マーク・ジョンソン
文:ジョン・デュラント
ジョンソンは写真家ならだれもが夢見る人生を送っている。人の心を瞬時につかむ彼の作品は、この世のものとは思えない。それらはLAでもっともヒップなギャラリーに展示されており、物理学者や美術史家といった人々が、ニトロ入りの言語で論理的批判をくり広げる対象にもなっている。まるで視覚パズルのような彼の作品は、ぼくたちが持ち得る写真の知識や時間という概念に挑戦してくる。
When The Baseline Thumps
「ベースが鳴り響くとき」
木工室からヒップホップまで…、ショーン・ステューシーの半生
文:クリスチャン・ビーミッシュ
「ベースが響くと鳥肌が立つ」。ステューシーおなじみの字体で書かれた広告のキャプションだ。横にはブリッツによって瓦礫の山となったロンドンの街に佇む、イギリス人学生と思われる人物を捉えた古い写真が並んでいる。写真とそのメッセージは、ピンテールのシングルフィンをシェープしていた事実からはあまりにもかけ離れているように思える。1973年ごろ、彼はハンティントンビーチのクオンセットハットにあったラッセル・ブラザーフッド・サーフボードで働いていた。しかし、いずれにしても「ベースが響く」ことに達したのは、彼の音楽的嗜好の進化の過程では当然の帰結だった。
Get Busy Living
「全力で生きる」
シェーン・ドリアンの肝っ玉物語
文:ジェイミー・ブリシック
ポートレート:ショーン・デュフレーヌ
その日の午後、ぼくは真っ青の水平線と同化したインフィニティプールの、カフェフラというオープンテラスのレストランでシェーンとリサに会っていた。ぼくはリサに、モンスターウェーブに乗るのが仕事の男と結婚生活を送るのはどんな感じなのか訊ねてみた。タンクトップに黒髪で優しそうな顔をした彼女は肩を震わせながらこう言った。「怖いわ。ものすごく不安だし、ぜんぜん楽しくない。わたしの母がいい表現をしていたわ。わたしは兵士の妻のようだって。家族のためにわたしがしっかりしないと、シェーンが仕事に集中できなくなってしまう。シェーンが居ようが居まいが、わたしに家庭を引っぱる意気込みがないと成りたたないのよ。だっていつ彼がスウェルに呼ばれるかなんてわからないから」
Tagalog Connection
「タガログコネクション」
1980年代終盤、フィリピンにサーフキャンプを建てたひとりの日本人
文:李リョウ
1980年代の終わりごろ、「あそこは波の宝庫」と聞いただけでフィリピンにサーフキャンプを建てた日本人がいた。当時、まだクラウド9もモナリザも発見されていなかったフィリピンは、マルコス政権が倒れ、マニラにはゴミがあふれ、政情は混迷を極めていた。それでも男は、ゲリラが出没する峠を越えて海辺の町バレアをめざした。そこは映画『地獄の黙示録』のロケがおこなわれた場所で、辺りのジャングルは黒焦げになっていたという。これはその男の足跡と再訪のストーリーだ。
Where Silence Reigns
「静寂が支配する場所」
音のエコロジスト、ゴードン・ヘンプトンが守りたい、1インチ四方(2.5㎠)の静寂の地
文:ギャヴィン・エーリンガー
写真:ショーン・パーキン
シアトルのピュージェット湾を見下ろす、湯気が立ちこめるカフェ。皿のぶつかりあう音、卵の焼ける音、人々の賑やかな話し声。そんな音の中に、霧を晴らすような勢いで船の霧笛が響き渡る。静寂の保護を使命とする男と、この音の渦の中で会っているなんて、皮肉ではあるが、じつは最適な状況なのかもしれない。1インチ四方の静寂を守るということ。それは、とても壮大かつ無謀な任務であることを、ぼくはすぐに知ることになる。
The Big Wave Riders Of Hawaii
「ハワイの大波に挑むビッグウェーバーたち」
ベルナード・テストメイルによるコロジオン湿板(しっぱん)写真
文:ジェイミー・ブリシック
「サーフィンの世界は最後の自由の楽園だ」とテストメイルは言う。彼のコロジオン湿板写真への情熱は裏返せばデジタル写真への失望だ。ポートレートにたいし思いやりや目的意識の高いアプローチを切望していた時期、写真技術の歴史を徹底的に学び、ビッグウェーブ・サーフィンと相通ずるプリミティブで人と自然が対峙する瞬間を切り取る湿板写真にたどり着いた。
「タウンは変わらず」
ワイキキのリーフ、ストリート、人々、周辺地域。心と身体の帰還
文:デビッド・ウォング
ぼくは島から7年間も離れ、メインランドに住みついたケイキ・オ・カ・アイナだった。ぼくはようやくここへ帰り、砂をかぶりひび割れたカイザースの駐車場を歩いていた。シャワーの前を通り、小さなビーチへ向かう。ポイドッグをなでて、深呼吸してストレッチをした。サムライ全員が撃たれる映画の話をしているアンクルがいた。あっという間に干からびる水たまりに捕まった蜂がもがいている。チャンネルをカヌーが走っていった。岩の上では大きなカーキ色のパンツを穿いた中国人が太極拳をおこなっている。ロングボードのワヒネがあまりにも美しく波に乗るので、ぼくは若返った気分でちょっとウキウキした。死んだリーフは沈んだ墓地のようだった。
Spacetime
「スペースタイム」
波の一生を一枚の写真で表現する写真家、ジェイ・マーク・ジョンソン
文:ジョン・デュラント
ジョンソンは写真家ならだれもが夢見る人生を送っている。人の心を瞬時につかむ彼の作品は、この世のものとは思えない。それらはLAでもっともヒップなギャラリーに展示されており、物理学者や美術史家といった人々が、ニトロ入りの言語で論理的批判をくり広げる対象にもなっている。まるで視覚パズルのような彼の作品は、ぼくたちが持ち得る写真の知識や時間という概念に挑戦してくる。
When The Baseline Thumps
「ベースが鳴り響くとき」
木工室からヒップホップまで…、ショーン・ステューシーの半生
文:クリスチャン・ビーミッシュ
「ベースが響くと鳥肌が立つ」。ステューシーおなじみの字体で書かれた広告のキャプションだ。横にはブリッツによって瓦礫の山となったロンドンの街に佇む、イギリス人学生と思われる人物を捉えた古い写真が並んでいる。写真とそのメッセージは、ピンテールのシングルフィンをシェープしていた事実からはあまりにもかけ離れているように思える。1973年ごろ、彼はハンティントンビーチのクオンセットハットにあったラッセル・ブラザーフッド・サーフボードで働いていた。しかし、いずれにしても「ベースが響く」ことに達したのは、彼の音楽的嗜好の進化の過程では当然の帰結だった。
Get Busy Living
「全力で生きる」
シェーン・ドリアンの肝っ玉物語
文:ジェイミー・ブリシック
ポートレート:ショーン・デュフレーヌ
その日の午後、ぼくは真っ青の水平線と同化したインフィニティプールの、カフェフラというオープンテラスのレストランでシェーンとリサに会っていた。ぼくはリサに、モンスターウェーブに乗るのが仕事の男と結婚生活を送るのはどんな感じなのか訊ねてみた。タンクトップに黒髪で優しそうな顔をした彼女は肩を震わせながらこう言った。「怖いわ。ものすごく不安だし、ぜんぜん楽しくない。わたしの母がいい表現をしていたわ。わたしは兵士の妻のようだって。家族のためにわたしがしっかりしないと、シェーンが仕事に集中できなくなってしまう。シェーンが居ようが居まいが、わたしに家庭を引っぱる意気込みがないと成りたたないのよ。だっていつ彼がスウェルに呼ばれるかなんてわからないから」
Tagalog Connection
「タガログコネクション」
1980年代終盤、フィリピンにサーフキャンプを建てたひとりの日本人
文:李リョウ
1980年代の終わりごろ、「あそこは波の宝庫」と聞いただけでフィリピンにサーフキャンプを建てた日本人がいた。当時、まだクラウド9もモナリザも発見されていなかったフィリピンは、マルコス政権が倒れ、マニラにはゴミがあふれ、政情は混迷を極めていた。それでも男は、ゲリラが出没する峠を越えて海辺の町バレアをめざした。そこは映画『地獄の黙示録』のロケがおこなわれた場所で、辺りのジャングルは黒焦げになっていたという。これはその男の足跡と再訪のストーリーだ。
Where Silence Reigns
「静寂が支配する場所」
音のエコロジスト、ゴードン・ヘンプトンが守りたい、1インチ四方(2.5㎠)の静寂の地
文:ギャヴィン・エーリンガー
写真:ショーン・パーキン
シアトルのピュージェット湾を見下ろす、湯気が立ちこめるカフェ。皿のぶつかりあう音、卵の焼ける音、人々の賑やかな話し声。そんな音の中に、霧を晴らすような勢いで船の霧笛が響き渡る。静寂の保護を使命とする男と、この音の渦の中で会っているなんて、皮肉ではあるが、じつは最適な状況なのかもしれない。1インチ四方の静寂を守るということ。それは、とても壮大かつ無謀な任務であることを、ぼくはすぐに知ることになる。
The Big Wave Riders Of Hawaii
「ハワイの大波に挑むビッグウェーバーたち」
ベルナード・テストメイルによるコロジオン湿板(しっぱん)写真
文:ジェイミー・ブリシック
「サーフィンの世界は最後の自由の楽園だ」とテストメイルは言う。彼のコロジオン湿板写真への情熱は裏返せばデジタル写真への失望だ。ポートレートにたいし思いやりや目的意識の高いアプローチを切望していた時期、写真技術の歴史を徹底的に学び、ビッグウェーブ・サーフィンと相通ずるプリミティブで人と自然が対峙する瞬間を切り取る湿板写真にたどり着いた。
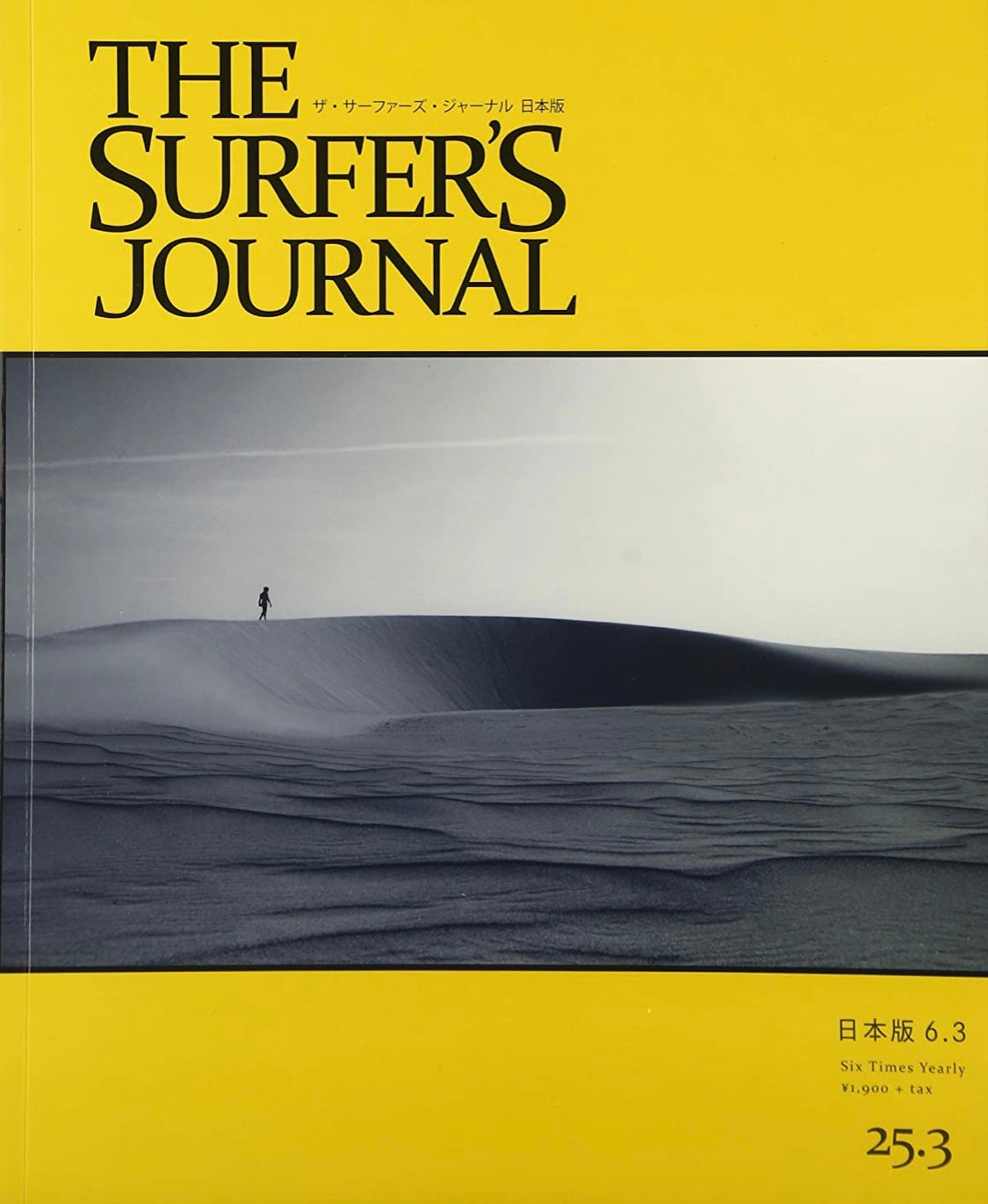
6.3 / ザ・サーファーズ・ジャーナル日本版
セール価格¥2,090
通常価格 (/)











