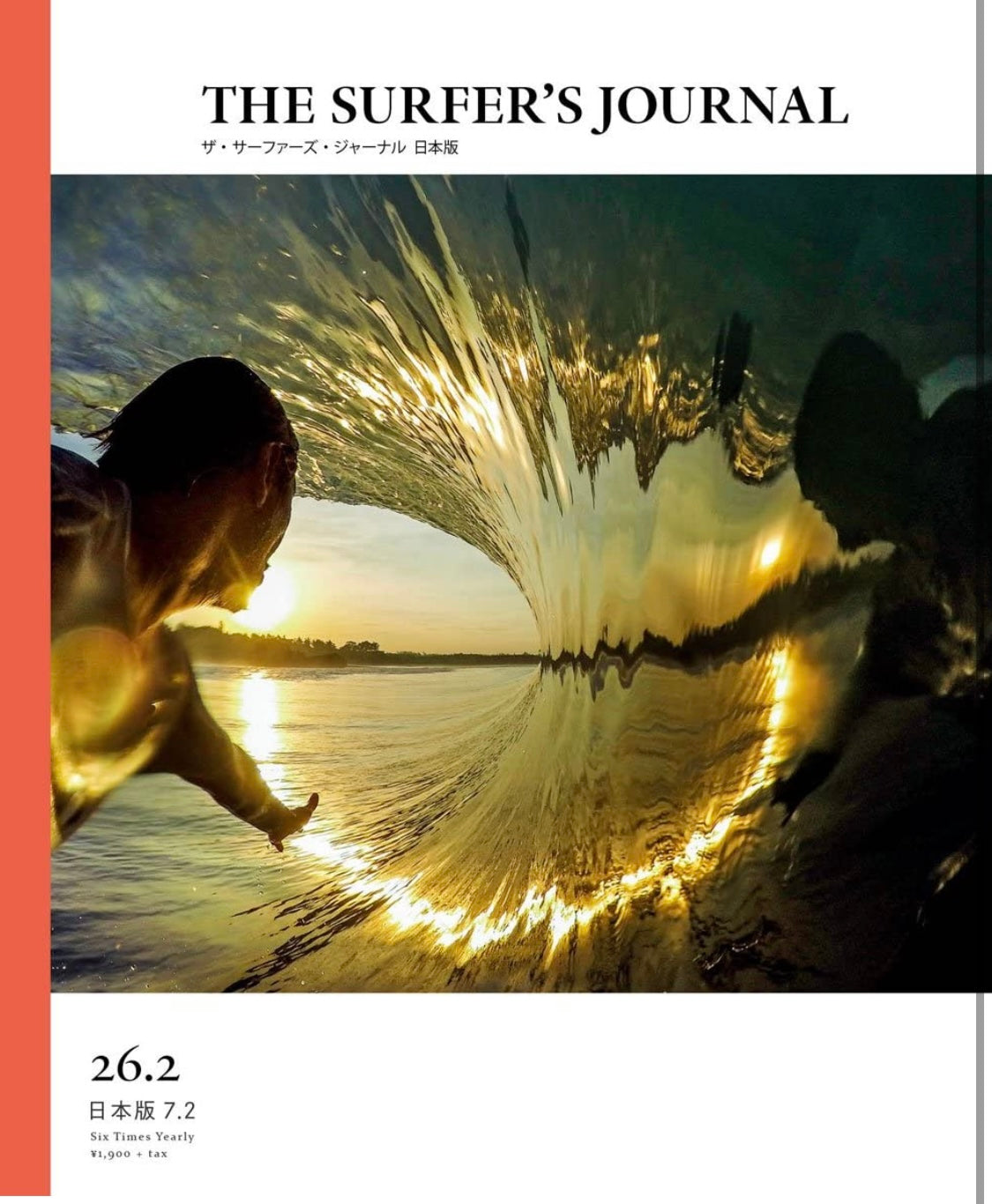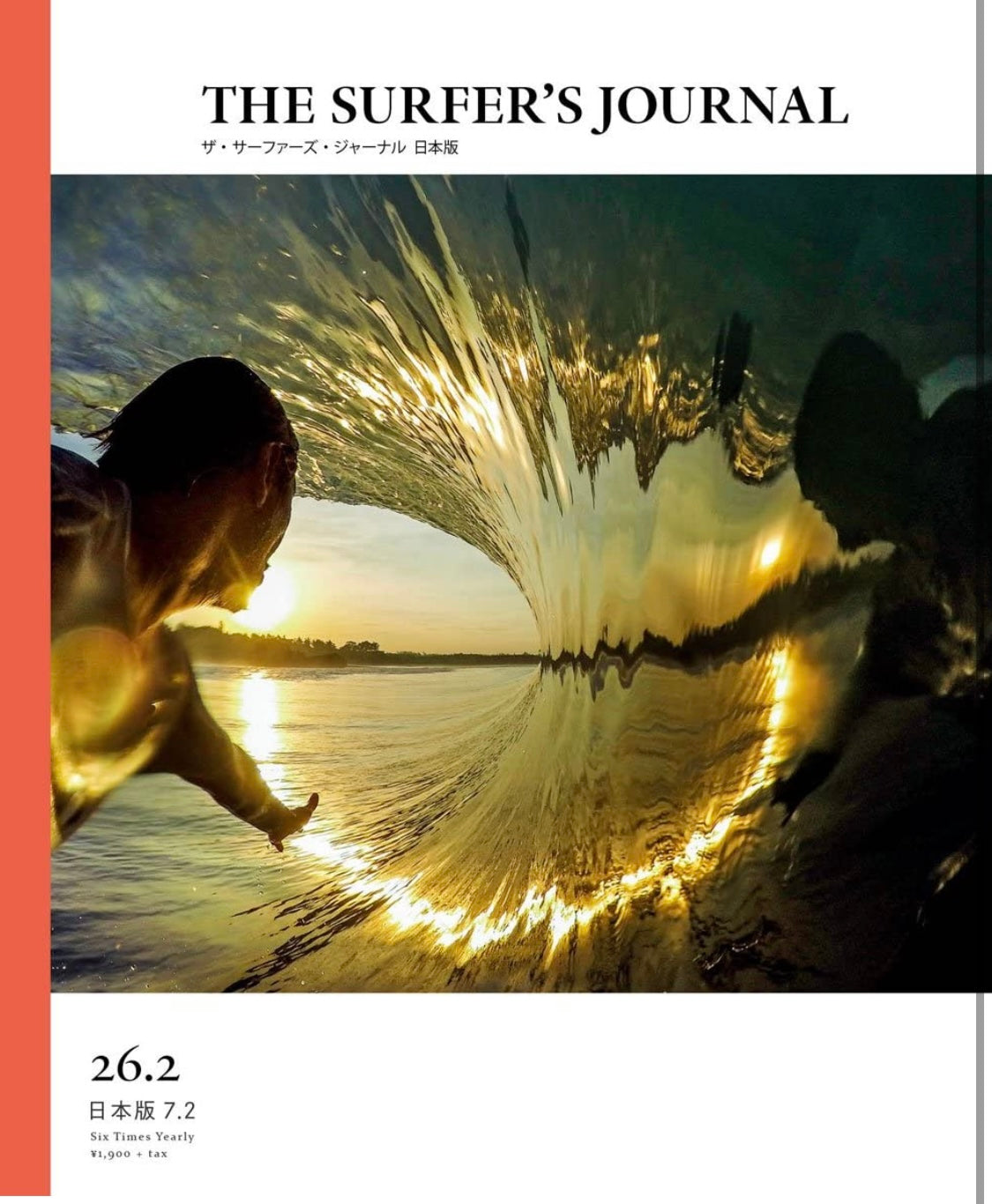
7.2 / ザ・サーファーズ・ジャーナル日本版
税込み価格
Chasing The Elusive Dream
「1969年、海外に目を向けた4人のサムライ」
文:森下茂男
日本のサーフィン黎明期におけるサーファーたちの時代マインドには、“誰が一番乗りか?"という先陣争いがあった。それは、いつサーフィンしたのかにはじまり、誰が最初にこの波(ポイント)をサーフしたのか、また、誰が最初にサーフボードをつくったのかといった「一番乗り」競争があり、そして誰がいちばん初めに海外の国際大会に出場するのかといった一番乗りレースもそのひとつだった。
Starting From Scratch
「日本サーフィン連盟設立前夜」
文:森下茂男
東京オリンピックの正式種目決定を受けて、悲願だった日本体育協会加盟など、にわかに慌ただしくなった日本サーフィン連盟周辺だが、日本のサーフィン黎明期にその礎の、さらに礎を築いた男たちがいた。
Going Lala
「ゴーイング・ララ」
じつは奥深いパフォーマンス・サーフィンの歴史。
文:デイブ・パーメンター
崩れる前の波のフェースを横に滑りはじめたのは、いつごろなのか。材料が限られ、デザインが未発達だったとしても、だれかが偶然、もしくはトライ&エラーの末、斜めに滑ることを発見した可能性は排除できないだろう。ポリネシア・トライアングルの底辺あたりでは短いベリーボード風の乗り物が使われていたが、サーファーたちがそれに乗ってララに興じていたことも、じゅうぶん考えられる。どれも推測の域を出ないものの、ひとつだけ確かなのは、サーフィンが今日の姿にたどり着いたのは、ポリネシアの海洋民族がハワイ諸島に定住した後ということである。
SOUNDINGS
「ロッカー:波にフィットするということ」
クリスチャン・ビーミッシュによるシェーパーたちへのインタビュー
文:クリスチャン・ビーミッシュ
はたしてシェーパーは、サーファーが喜ぶマジックなカーブを見つけられるのだろうか? たとえば1990年代に時代を席巻したケリー・スレーターのショートボード。そのミニマリズムはきわめて実験的な試みだった。一般サーファーのだれもが、その「妖精の靴」を手に入れて、彼のようにスピードとフローを体感したいと思ったが、多くは徒労に終わった。だが、その軽く薄いサーフボードの10年が、大きな沈滞だけを招いたわけでもない。マット・ケックルが指摘するとおり、1990年代に開発されたフリップチップ集積回路は、パワー・フロー・サーフィンとエアリアルという新境地の実現に向けた橋渡しにはなっただろう。
そのほか、The Chocolate Islands「チョコレート・アイランズ」サントメのルーツに触れる旅や、疾風のように駈け抜けたニューヨークのサーフレジェンド、リック・ラスムーセンの人生を描いたUnsafe At Any Speed「危険がいっぱい! 」や、イギリス在住フォトグラファーのファイル、Portfolio: Al Mackinnon「ポートフォリオ:アル・マッキノン」などなど、今号も話題のストーリーが満載です。