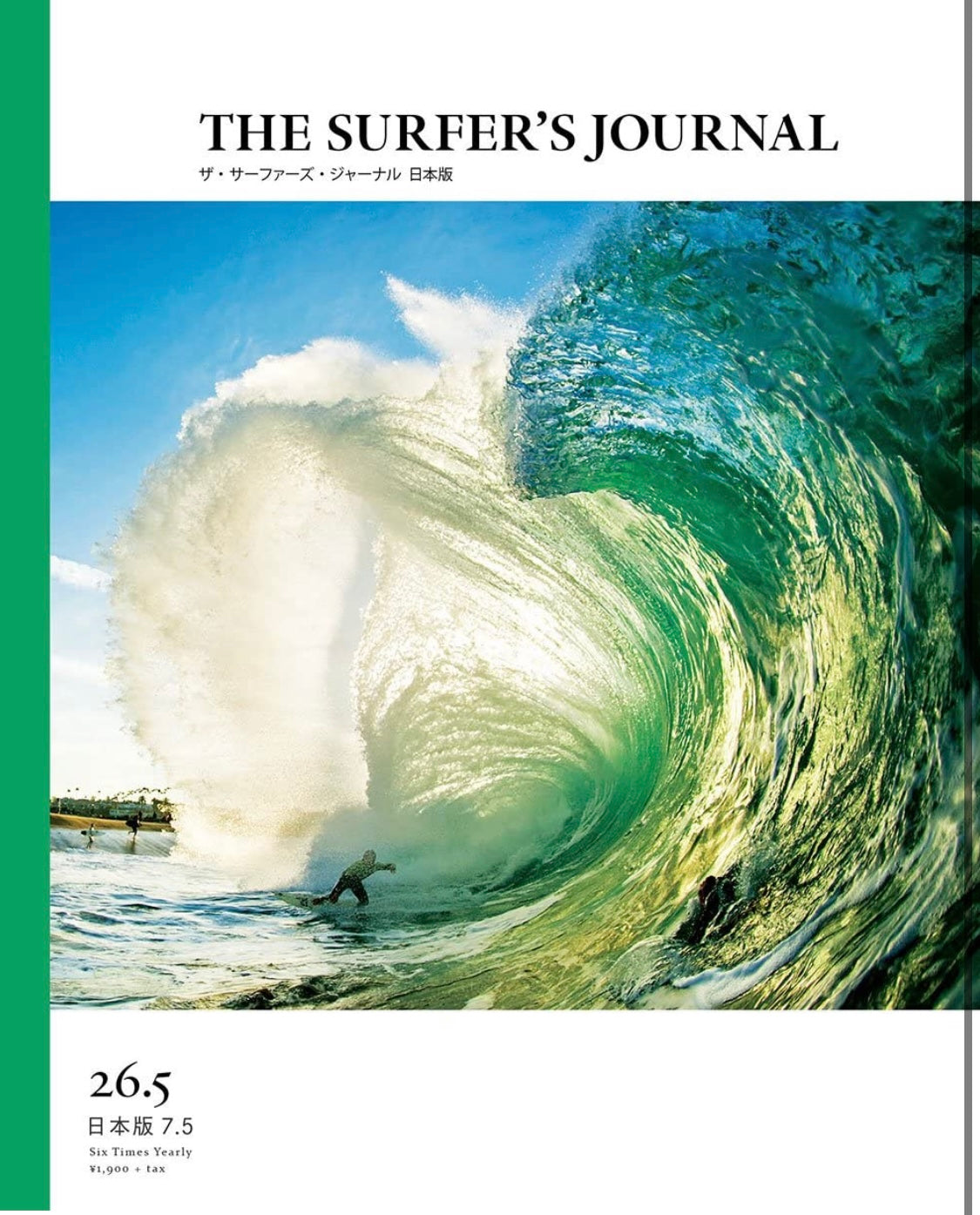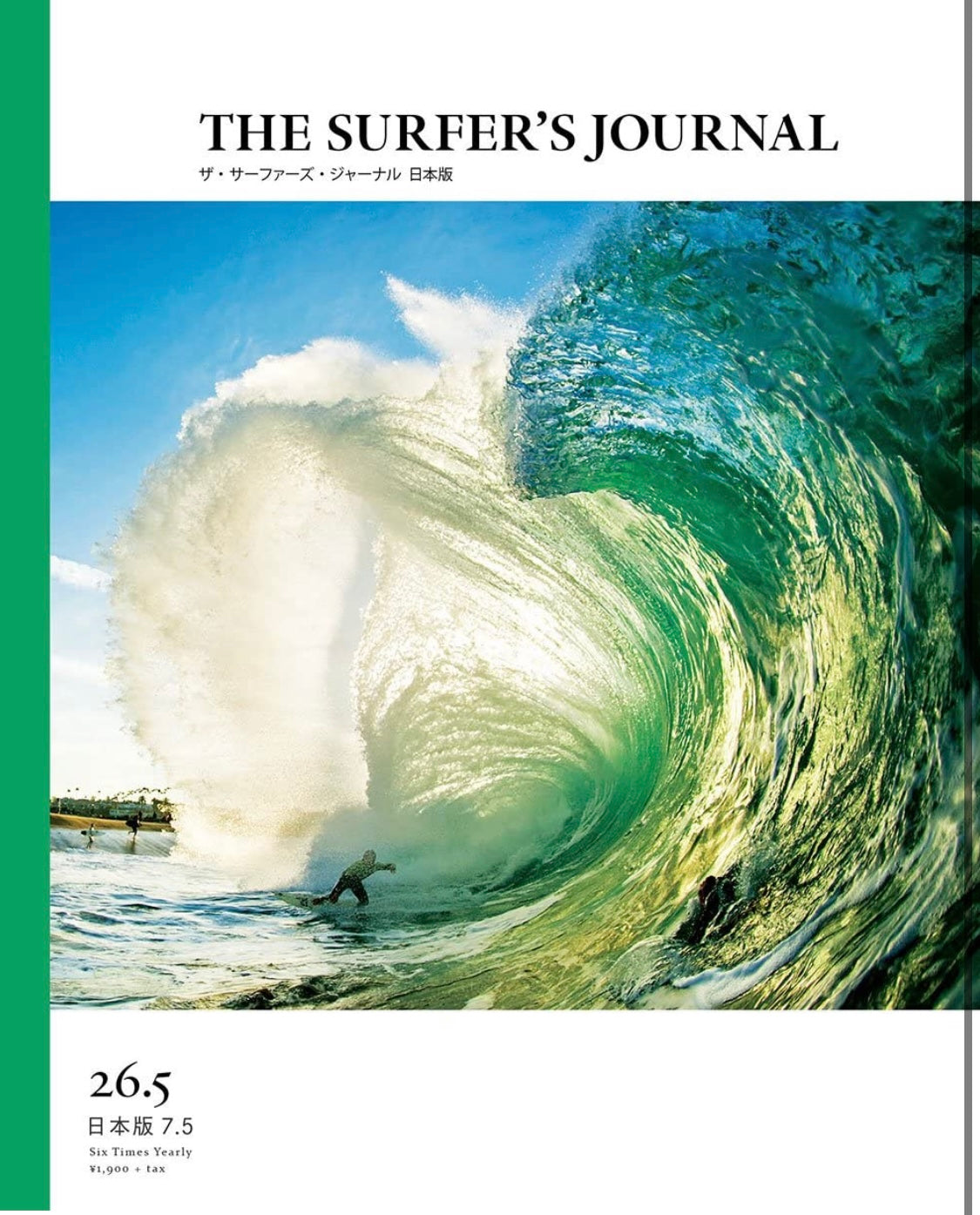
7.5 / ザ・サーファーズ・ジャーナル日本版
税込み価格
フィーチャーストーリー
最初のフィーチャーストーリーは、日本版のオリジナルコンテンツ、国産下町ボードビルダーであり、日本サーフボード産業の揺籃期における日米のサーフボードビルダーたちの橋渡し的な存在でもあったテッド・サーフボードを立ちあげた阿出川“テッド"輝雄の物語である。
INNER CITY, OUTER SEA
「アメリカの空気を嗅いだ男、テッド阿出川とテッド・サーフボード」
文:森下茂男
のちにテッド・サーフボードを立ちあげることになる阿出川“テッド"輝雄は、日本大学芸術学部(以下、日芸)放送学科3年のとき(マイク真木は放送学科の1年後輩に当たる)に渡米する。彼が21歳、1964年の春、新しいものを自分の目で見たいという思いから、知り合いを頼ってカリフォルニアのサンタモニカに向かう。
つづいての物語は、テッド阿出川がアメリカから輸入した1台のプレーナー、スキル100はテッド阿出川をはじめ数多くの日本のシェーパーたちに引き継がれ、技術とともに日本のサーフボードインダストリー史を支えたのだった。
THE PLANER THAT COULD
「スキル100物語 since1967」
日本のサーフボードインダストリー史を支えた1台のプレーナー。
文:星静雄
「東宝商会を通じ、機械輸入商からこのスキル社のプレーナーを輸入したのは、1967年の夏の終わりだったかなあ」 阿出川は、その前々年はハモサに住み、シェーパーだったハワイのハロルド•イギーがすでに使っていたスキルに魅了され、その必要性を感じていた。さっそくオーダーすると、このスキルは意外にすんなり入手できたという。ともすれば正規輸入第1号であってもおかしくはないし、その後約30年間つづくクラーク・アンド・スキル時代以前から、このスキルが日本に存在していたと思うと、それはとても夢のある話ではないか。
アメリカのサーフシーンを支えた米『サーファー』誌と米『サーフィン』誌。そのひとつ『サーフィン』誌が廃刊になった。元『サーフィン』誌の編集長、ニック・キャロルがその思い出を語る。
Let' Do It!
「レッツ・ドゥー・イット! 」
米『サーフィン』誌の元エディター、ニック・キャロルの回想録。
文:ニック・キャロル
最後は静かに訪れた。いっきにバタンとではなく、名残惜しそうに。皮肉なことに、廃刊のニュースはソーシャルメディアを通じて表面化した。定期購読の更新時に、自動音声応答サービスで最終号が出荷済みと知った読者が投稿したのだ。 しかし当の出版元は、投稿が引き金となってフェイスブックに猛烈な勢いでコメントが殺到するまで口を固く閉ざし、53年もつづいたサーフメディアは無言のまま幕を下ろした。
医師だったら、死亡診断書になんと記すだろうか。大衆はインターネット隆盛のせいにしたり、サーフ産業衰退の兆しと受けとめたが、そのどれもが近因にすぎない。根本の原因はプリント・メディアの終焉ではなく、読者層の変遷につぐ変遷にほかならない。『サーフィン』誌が創刊された1964年以降、何百ものサーフィン雑誌がアメリカだけでなく世界中に誕生し、そのいくつかは今なお強い影響力をもっている。創刊当時、アメリカ沿岸部に住む人々の3割近くが21歳以下(それはオーストラリアにも当てはまる)だったのに対し、現在は55歳以上の人口がおなじ割合を占めている。若いエネルギーが口火を切り、牽引してきたモダンサーフィンのムーブメントは鳴りをひそめ、若手サーファーの人口は、いまや全体のほんの一部にすぎない。
GET CLIP
「ゲット・クリップ」
社会を生き抜くためのセルフ・ディスカバリー(自己啓発)について。
文:ジェイミー・ブリシック
「映画『セルフ・ディスカバリー』が2017年現在のサーフ・ムービーのあるべき姿の一部を捉えているのかもしれない」。そう力説するリチャード・ケンビン。「1970年代にぼくらが観て育った当時のムービーは、サーフィンと音楽、それがすべてだった。勝手にジミヘンやストーンズの音楽を使っていた。すばらしい時代じゃないか。サーフィンと音楽の融合は、ぼくにとって衝撃だった。アートを追求する職人気質のクリスとすべてのスタッフに大いなる敬意を表したい」
CALL ME AT THE CRACK OF NOON
「午後になったら電話して」
アーティスト、ファム・ファタール(フランス語で魔性の女)、女神 ―
ノースショアの歴史を語るうえで欠かせない女性。
1970年代のサーフ・フォトグラファー、シャーリー・ロジャーズの物語。
文:ボー・フレミスター
写真:シャーリー・ロジャーズ
1970年代の写真の中に、あるひとつの偶像的なイメージがある。褐色の肌をした水着姿の女性がノースショアのビーチで撮影している姿を捉えた写真がそうだ。いや、ひとつと言ったが、ハリウッド・スタイルの立派な三脚を砂浜に立てて、巨大なロングレンズを覗き込むこの女性の写真は、じっさいは山ほど残されている。若くて健康的でエキゾチックな写真の中の彼女は、腰に手を置き額に汗をかきながら、全身で被写体を挑発している。「さあ坊や、私を楽しませて」と。
天国まで届いて、神さまも赤面させてしまいそうな美脚。声をかけるのに相当な勇気をふりしぼらないと近づけない、そんな女性。手のひらにひょいと乗せられて、拳で粉々に握りつぶされ、エッセンスを海に投げ捨てられてもおかしくない。しかも、そんな仕打ちを受けても、よりよい存在に生まれ変われそうだと思ってしまうような、そんな女性だ。
PORTFOLIO: ED SLOANE
FOR NOW
「現在進行形」
オーストラリアのビクトリアから飛びだした天然色。